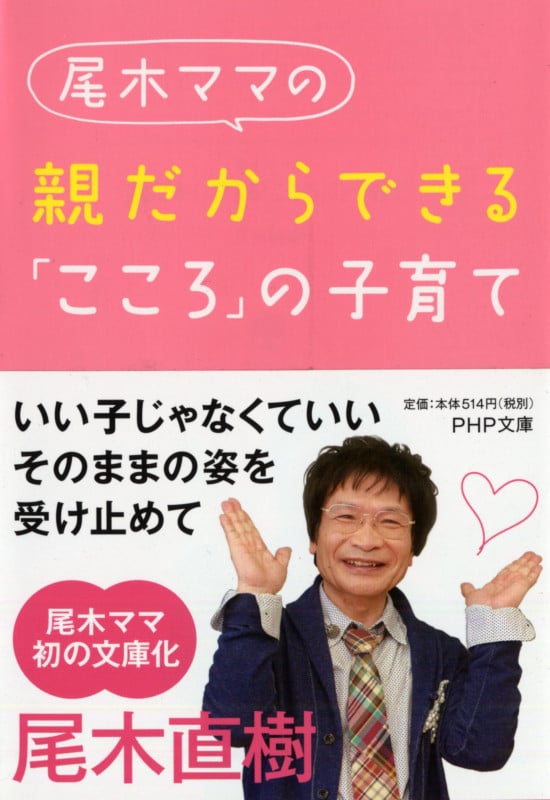今回は、「尾木ママ」で有名な、尾木直樹先生の著書です。
子育てにおいては、子どもの「こころ」の面のケアも大切です。
「こころ」の子育てや、尾木ママに興味のある方、是非お勧めの一冊です。
「こころ」の子育ての大切さ
「こころ」の子育てとは何でしょうか?
子どもの心が健全にすくすく育つように、子どもの心の発育に配慮した子育てのことです。
心が育つと何がいいのか
心が健全に育った子どもは、大きくなった時に「自分らしく生きられる」ようになります。「自分らしく生きられる」子どもは、「自らどう考え、判断し、問題を解決していく力や、豊かな発想力に基づいて、様々に想像していく力」が身につきます。そして、生きる力や意欲、そして自己肯定感を持てるようになります。
よい子ストレス
調査結果によると日本の子どもたちは自己肯定感が低いと言われています。自己肯定感の低い子どもは、自分のありのままを出せなくなります。その結果、自分らしく生きられなくなります。
子どもたちの自己肯定感を低くさせている原因の一つに「よい子ストレス」というものがあります。これは、主に親が子どもに「よい子像」を押し付けることによって生じるストレスです。
最近は、「親の前ではよい子に変身する」子どもたちが増えてきているそうです。「お母さんの前ではいつもお利口さんでいなければならない」と、子どもたちは必死によい子を演じているのです。親は、「よい子像」を、あらゆる場面で子どもに要求し、子どもは親の前で演技せざるを得なくなります。残念なことに、そのような子供たちは、「あるがまま」では親に受け入れてもらえないとわかっているのです。
よい子を演じ続けるとどうなるか?
よい子を演じきった先にあるものは、「自分らしさ」の空洞化です。自分とはなにかと考えたときに自分がない。「自分が何をしたいのか」が分からなくなり、就職などの進路を決めるときに大変悩みます。それが深刻化すると、突然キレてしまって事件を起こしたり、ひきこもってしまう。
かく言う自分自身も実は、つい最近までは、一体何をしたいんだろうとよく悩んでいました。中年のおじさんになってもです。自分の好きな事さえも分からなくなっていました。それは長年、他人の用意したものさしで生きてきたからだと思っています。たとえ、どんなにいい学校を出ても、いい企業で働けても、自分が何をしたいかがはっきりしていなければ、心が満たされることは一生ないのだろうと思います。
親として、子どもにはそうならないように導いてあげたいですよね。
自己肯定感の大切さ
「自分らしく生きられる」子どもは、自己肯定感が高いという特徴があります。自己肯定感が高い子どもほど、生きる力や意欲がわき、様々なことに前向きに取り組めるようになるからです。そして、「自分らしく生きられる」力をどんどん身につけていけます。
これが何年も積み重なっていきますので、長期的にみると非常に大きな差が出てきます。人生を左右するといっても言い過ぎではありません。自己肯定感はこのように、子どもの将来をも左右するものです。親としては自己肯定感を高めてあげられる育て方をしてあげたいものですね。
では、どうすれば子どもの自己肯定感を育むことができるのでしょうか?
自己肯定感はアウトソースできない
自己肯定感はどこで身につけられるのか?
学校?塾?習い事?どれも違います。
答えは「家庭」です。
この本のタイトルの一部「親だからできる」に着目してみましょう。「親だからできる」です。逆に言うと、親でなければできないのです。したがって、塾に通わせる、習い事に通わせる、、、他の人にアウトソースしているだけでは決してつけてあげられないもの、それが「自己肯定感」なのです。
自己肯定感を高める育て方とは?
まずは、ありのままを受け入れられる安心感です。
親としてしてあげられることは、「安心感」を育んであげることです。それは、子どものありのままを受け入れてあげることから始まります。
どんなに言うことを聞かなくても、出来が悪くても、まずは「あなたの全てを受け入れますよ」という姿勢を見せて、子どもを安心させることから始まるのです。
家庭生活の大切さ
子どもの心を育む過程において、家庭でのコミュニケーションが重要です。
ダジャレのようになりますが、「子どもの心が育つのは、家庭(カテイ)の過程(カテイ)です」
以下は、私の心に響いた「子どもの自己肯定感を上げるために親が子どもにしてあげられること」3選です。どれも、決して特別なことは必要なく、日々の生活の中で実践できます。
- スキンシップを大切にする
- 愛と自信を与えるために叱る
- 食事を通じてコミュニケーションをとる

1つずつ見ていきましょう。
スキンシップを大切にする
一つ目の方法はスキンシップです。スキンシップをたくさんとってあげましょう。中学生でさえも、親とのスキンシップを求めています。それより小さい小学生ならなおさらです。チンパンジーの子どもも同じです。スキンシップは、年代や種を超えて共通に、安らぎや自信を与えてくれるものなのでしょう。考えてみれば、大人もそうですよね。スキンシップを通じて大人も子どもからたくさんの愛をもらうことができます。
最近は、子育てにおけるスキンシップの重要性が何一つ理解されずに、親と子の心のふれあい、肌のふれあいについて、まったく無頓着になっている親子関係が見られるようです。
スキンシップによって、以下のメリットが期待できます。
- 子どもが健やかに育ち、他者への思いやりも豊かになる
- 自分の殻を破ってどんな困難にも挑戦できる。
これらのメリットは、子どもが安心感で満たされることで生じるものですね。
愛と自信を与えるために叱る
2つ目の方法は叱り方です。手を出したり、怒鳴ったり激しく怒りをぶつけるだけの叱りになっていませんか?
自分もそうなんですが、叱るのってとても難しいですよね。親自身も上手に叱られてきていないから、子どもを上手に叱れないらしいです。我々の世代で、その連鎖を断ち切りましょう。
まずは、叱る理由のマインドセットを整えましょう。
- 愛を伝えるため
- 自信を与えるため
今までの概念がひっくり返りませんか?このように考えて叱っている親ってとても少ないのではと思います。自分は、「子どもの間違いを正すため」とか「他人に迷惑をかけないため」とかが思い浮かびますが、そんな理由では子どもには響かないのです。
また、子どもを自分の思うようにコントロールするために叱ることもよくないです。親に対する忠誠心は育っても、よい子を演じさせることにつながってしまいます。
愛を伝えるために叱る
自分を愛し、見守ってくれる他者の存在を確認できるとき、人間は安心します。子どもも、親から愛されると実感できれば、安らぎ、うれしく感じます。
叱るという行為は、親の想いを子どもに伝えるということ。これを愛情をもってできれば、叱るという行為にネガティブな感情は湧かないはずです。子どもにとっては、見守ってくれているのですから。
叱られたときに子どもが、うれしいと感じられたら、それが正しい𠮟り方なのです。
子どもがうれしいと感じられる叱り方をする
まずは、叱るという行為からネガティブなイメージを取り払いましょう。
自信を与えるために叱る
叱るべき行為は、悪なのかもしれませんが、悪いことをしたと理解できる力と、前進しようという力を子どもに与えることで自信に変わります。
自信になるための叱り方のポイントとしては、「認めて叱る」ということです。
認めて叱れば自信につながる
子どもを叱らなければならない場合でも、何かしら認めてあげられることはあると思います。以前に比べて成長している点を探し、「この点については、前よりもよくなったね、成長したね」と伝えてあげる。そうすれば、子どもは「前進したんだ。頑張った部分は、これでよかったんだ。親はちゃんと見てくれているんだ」と思い、自信をつけます。
叱り方のポイント
まとめとして、叱り方のポイントを5つ挙げておきます。
- まず、「どうしたの?」と聞く
- 失敗した辛さの「受け皿」になってあげる
- 失敗の中に「輝き」を見つけてあげる
- 「逃げ道」を作ってあげる
- 「学び」の機会とする
子どもは、悪意があって悪いことをしているのではありません。必ず子どもなりの理由があります。それをしっかりと聞いてあげる。
そして、そうせざるを得なかった辛さに共感してあげます。また、失敗の中にも、子どもなりに考えてやったことや、成長した部分があるはずです。そこをほめてあげましょう。
子どもも人間です。これから気を付けると言っても、またやらかすこともあるでしょう。それも認めてあげる。
そして、叱ることは決してネガティブなものではなく、子どもの成長のための学びの機会であると捉えましょう。
食事を通じてコミュニケーションをとる
最後に3つ目の方法は、食事のとり方です。
孤食の問題点
皆さんは、お子さんと一緒に朝食をとっていますか?忙しい朝にそんなこと無理。みんな自分の好きな場所で、タイミングで、食べたほうが良い。そんな方も多くなっているようです。
「孤食(=個食)」という言葉をご存じでしょうか?
「小学生が子どもだけで、朝食をとること」ですが、平成19年の調査では、小中学生の41%が孤食をしているようです。
この孤食は何が問題かというと、コミュニケーション不全につながるという点です。コミュニケーション不全を大人になってもこじらすと、「ひきこもり」にならざるを得ないのです。当然、自己肯定感が低い大人になります。
食事を通してコミュニケーション力をつける
家族は対人トレーニングの土台です。対立したり和解したり、日常経験から相手との折り合いの付け方や、喜びの共有法を身につけていきます。食事は、そのための絶好の機会になるのです。
食事中は味覚を通して好悪感情をダイレクトに感じ取り、共有することができます。食卓を囲みながらの会話で家族と交流できます。また、家族のちょっとした変化をつかめるようになり、他者認識力も身につきます。後片付けも協力して行えます。朝夕の食生活を家族と過ごしていれば、学校でのコミュニケーションは大丈夫でしょう。
このように「心」と「心」のコミュニケーションを実現できる。食事は、コミュニケーション力を鍛えるとても重要な場なのです。
他愛のない会話の積み重ねがいい
私はというと、毎日子どもたちと朝食、夕食をとるようにしてます。朝は特に忙しいですが、前日の夕食の残りなど簡単に準備をできるようにし、時間を作って、子どもと食卓を囲むようにしています。
食事中に「昨日は、学校でなにしたの?」とか「給食何だった?」とか他愛のない会話をします。楽しい会話が出来さえすればいいのです。これを日々積み重ねていれば、コミュニケーション力が身についていきます。
子どもはいつか、親を離れて巣立っていきます。子どもと一緒に過ごせる期間は有限です。毎日の食事は、子どもと過ごす時間を最大化するためには絶好の機会なので、是非これを利用したいものですね。
まとめ
家庭での日常生活を基本とした「こころの子育て」。できることから始めてみませんか?
ちょっとしたことでも、毎日積み重ねれば、必ず効果は出てきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。